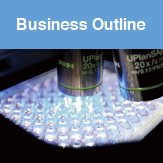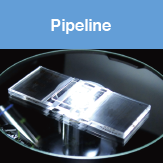- 第36回(12月28日)『例外のない規則はない』
-
There is no rule but has exception. 中学の時に特殊な「But」の使い方として試験勉強で覚えた諺です。色々な規則には例外はつきものです。それどころか,数多くの例外を初めから列挙したような規則すら見受ける事があります。物事は右・左,白・黒,善・悪といった二元論のみでは片付かない場合が多いのではないかと思っています。
我々は,医薬品開発にあたり,実に多くの規制に縛られています。前臨床試験や臨床試験の実施法に関してはICH(International Conference on Harmonization)が施行されており,様々なガイドラインが日米欧の製薬関連企業を中心に発表されています。更に,臨床試験ともなると,疾患別に各種の臨床試験実施・評価法に関するガイドラインが世界的に公布されていて,製薬企業は金科玉条の如く追随を迫られているかのように見受けられます。
しかし私は,ガイドラインはあくまで「ガイド」であり,単なる方法論ではなく,ある種の「哲学」ではないかと思います。よい品質のものを作ろう,優れた科学技術による評価を行おう,倫理性の高い臨床試験を実施しよう,という目標に対する視線のズレがなければ,ガイドラインにある語句はどのようにでも解釈が可能であり,一言一句間違いなく従うのではなく,科学的・倫理的妥当性を考慮した上で柔軟 に対応すればよいと考えるべきでしょう。アメリカのように規制当局とのフランクなディスカッションが可能な状態であれば,より上手く説得できるのではないかと思います。
昨今,バイオベンチャー企業の株式上場基準に関して,証券取引所は様々なガイドラインを出してきています。また,それらに付随した様々な風評も流されてきているようです。実際に多くのバイオベンチャーがその基準をクリアしようとして,それに特化した事業計画を練っています。中にはそうすることによって事業展開の軸足がズレてしまっている会社も見受けられるようです。しかし,自分達の描いた事業構想が上場審査基準には合わないものの,株式公開による資金調達が是非にも必要であると判断されたならば,事業計画に対するそれなりの合理的な説明が成り立てばよし,と考えた方がいいのではないかと思います。ガイドラインにも例外はあり得るはずです。
本年も多くの投資家の皆様や関係各方面の方々には大変にお世話になって参りました。来年度の当社のスローガン「選択と集中の年」を念頭に,日々事業発展に尽くして参りたいと思っております。どうぞ,今後ともご支援いただきますよう,宜しくお願い申し上げます。
社長コラム
社長コラム 2006
- 第35回(12月06日)『バイオは目に見えない』
-
私たちは自分の目で日常いったい何を見ているのだろうか,と思ってしまうことがあります。
科学雑誌などで,がん細胞を攻撃しているリンパ球や,モノクローナル抗体が細胞 膜分子標的に結合する様など,さもありなんのような美しい絵になっているのを見か けます。複雑な生命現象の世界を説明するのにはうってつけの方法だと思います。また,それらを見て,バイオに興味を持ったり,理解を示したりした人も多いと思います。しかし,それらはある現象を非常に簡素化したものであり,ごく一方向,一部分 を見ているに過ぎないことも忘れてはなりません。
電気機器や食品はそれ自体製品として目に見えます。自動車や携帯電話なども, 細かな部品まで覗こうと思えば,見ることができます。そこに製品があり部品がある のだと。しかし,医薬品は,実は目に見えません。そこに白い錠剤がある,とか,1本のアンプルがあって透明な液体が入っている,というところまでです。そこに一体何が入っているのか,その場では誰にも実際は見ることが出来ません。成分表を見 て,それを全面的に信じて,処方し,服用しているのが現状です。ただ,規制当局から認可された製品であるからには,それまでの開発期間に数々の品質試験をクリアー してきているので,心配には及びません。
しかし,目先をかえ,開発途上の製品であったならどうでしょう?低分子の医薬 品であれば比較的はっきりと分子構造まで特定でき,不純物のプロフィールまで チェックが可能です。しかし,そう簡単にはいかないのがバイオ医薬品の開発の難しさなのです。
品質試験として,遺伝子解析をし,アミノ酸分析をし,不純物のプロファイルを 検査し,PCRで遺伝子の量を決め,蛋白分析をし・・・・それでも心配の種はつきま せん。様々な品質試験を工夫して行い,最終産物を様々な角度から眺めなおし,「ほぼ本物に間違いなかろう」と言うところまで持ってゆくのも大変な作業なのです。
我々も開発品の品質チェックには日々最善の努力を傾けています。それでも時 折,思いもよらなかった結果に目を疑うことがあります。そんな時でもせっせと原因 追求のために複雑な資料を読み返すのが精一杯です。この目で見る事の出来ないバイオ製品の品質を追いかけてゆくことに,非常に歯がゆい思いをすることがあります。 よいバイオ製品を世に出すため,我々は日夜眼を凝らしながら,真実を見極める努力 を怠らないよう心がけてゆきたいと思います。
- 第34回(11月21日)『治験の空洞化への対策』
-
日本の治験が何故空洞化してきたか?
この点については,このコラムでも何度か書かせて頂いたことがあります。理由はいくつかあるのでしょうが,以下の4点に集約されると思います。
- 医師の臨床薬理学教育が遅れていて,トランスレーショナルリサーチをはじめとする臨床試験に対する理解とインセンティブに欠けている。
- 国民皆保険の日本において,治験に参加する患者側のメリットが曖昧である。
- 日本で臨床試験をする必要に迫られているのは外資系のメーカーで,本国からの強い指示が出ている場合。一方で,日本メーカー発の新薬は海外での臨床試験を先行させる。
- 規制当局側の審査体制が不十分で,特にバイオ新薬の審査や相談には必要以上に時間がかかる。
このような状況は何も昨今始まったものではなく,この「失われた10年」の間にジワジワと日本国内の製薬業界に広がっていったものと思われます。しかも,この時期には抗体医薬や遺伝子治療などの,旧来の低分子医薬とは考えの異なる新薬の開発が欧米で盛んになり,ようやく日本にも導入されてきた時期に重なります。
政府はこれまで生命科学に対しては重点投資を行ってきましたが,相変わらずその成果が上がらず,最近になって再び治験の空洞化に問題を投げかけています。これはあくまで官僚主体で行われ,有名機関にのみ資金をばら撒き,インフラだけを整えて内容を十分に吟味できなかった政府自らの政策の失敗でもあると思います。その先には当然,厚生労働省ならびに総合機構の体制整備の遅れもあげられると思います。
日本の治験の空洞化を埋める何か妙案はないものでしょうか。このままでは国内製薬メーカーの開発は,益々海外主導にならざるを得ないだでしょう。そして,海外でも未承認段階の医薬品については,規制当局の審査に必要以上に時間がかかり,海外治験データも容易に利用できない,という状況はまだ続くのでしょう。
乱暴な提案になりますが,いっそのこと,国内の規制当局の新薬審査部門を全て一括してアメリカFDAに組み入れてしまってはどうでしょうか。海外で許可になった新薬は一部,或いは相当の臨床試験が省略できることになっているわけですから,その都度メーカーがデータを取り寄せたり,翻訳したりする時間は無駄のような気がします。また,アメリカで治験を開始した新薬も,同時に日本でも治験が開始できるようなシステムに出来ないものでしょうか。
有効で安全な新薬が一刻も早く患者さんに投与されるためにも,規制当局は中途半端なメンツを捨て,FDAに頭を下げるのも,有効な手段かも知れません。
- 第33回(11月6日)『得たものと失ったもの』
-
今年3月17日にテロメライシンの治験届(IND)をFDA(アメリカ食品医薬品局)に申請していましたが,8月にようやく治験開始の許可がおり,去る10月31日に,記念すべき第1例目の投与が,Mary Crowley Medical Research Center(アメリカ合衆国テキサス州ダラス市)にてとり行われました。現在までに明らかな副作用は認められていないという報告です。
私たちのような小さなバイオベンチャー企業が,創業2年目にアメリカで新薬の臨床試験開始させる事が出来たことは,何ものにも変えがたい貴重な経験でした。しかしながら,FDAからの宿題事項が出されたことによって,我々は貴重な時間を失ったことも確かです。
人間誰しも自分が成し得た事は完全であり,仮に欠陥があったとしても,それは第三者には気付かれないだろう,いや,気付いて欲しくないと思うものです。我々もこの2年間に蓄積してきた数々の前臨床試験のデータには,当然大きな自信を持ち,数々のコンサルタントからも意見を聴き,早期の治験開始は間違いなしと思っていました。
自分達が完璧だと思ったことでも,必ず漏れがあるものです。少し心配だなと心に残った事柄が,後で問題になったという経験は誰にでもあると思います。今回の場合も,自分達だけは,今度だけは,違うのだという驕りがあったのかも知れません。特に,ウイルス製造における品質試験の考え方に関しては,まだ世界的なコンセンサスはなく,自分達の世界に慢心していたことは大いに反省すべき点だと思いました。
また,「有効である」や「特異的である」といった言葉遣いに関してもFDAからはきっぱりとした指摘がありました。データを客観的に判断すれば「・・・よりは実験的に優れている」といった表現がふさわしいというものです。この点も,私たちの視野が狭くなっていたと,考え直すよいきっかけになりました。客観的な情報を,治験を実施するという医療現場に上手く伝えることこそが我々の重要な使命であると再認識しました。
これまでに我々が得たものは,社員一人一人の貴重な経験となり,オンコリスバイオファーマの良きDNAとして,今後も受け継がれてゆくだろうと期待して止みません。
- 第32回(7月20日)『「まだ」か「もう」か』
-
先週末,弊社は六本木3丁目の新オフィスに引越しをしました。社員一同,気分も新たに創薬に挑戦する気持ちであふれています。起業して2年と4ヶ月で,3箇所目のオフィスになります。転居の理由は,社員が増えたこと,今後IPOに向けての人員増加に対応したい,一つのフロアーで社員のコミュニケーションを円滑にしたい,などが挙げられます。
とりわけ拘ったのは,ワンフロアーで仕事がしたいという社員の希望でした。これまで弊社は同じビルの2階と4階に分かれていました。しかし,同じ目標に向かい,同じ気持ちで仕事が出来ているのであれば,2フロアーに分かれていても問題はないだろう,と考えてきました。ところが,次第にスタッフも増え,一部の社員には別のビルに移動してもらうことにもなり,更には複数のプロジェクトの進捗管理も次第に困難な状況が発生してきました。
原因はひとつ。社員のコミュニケーションが不足がちになっていたという点に集約されました。会議や打ち合わせを増やすなど,それなりの努力をしてきたのですが,依然情報の共有化は円滑には進みませんでした。いくらITが進歩しても,メールを山ほど出しても,人間のニュアンスの隔たりまでは埋め尽くすことは出来ないようです。
今回のオフィスは,おかげさまをもちまして,30人の社員を収容できるスペースを確保することができ,各部署,各プロジェクトで心置きなくディスカッションができるようミーティングルームを3箇所設置することが出来ました。また,小さいながらもリフレッシュスペースを作るなど,社員の労働環境の改善に主眼を置いて設計させて頂きました。
弊社は7月11日にテロメライシンのINDに関する宿題事項の回答をFDAに提出し,臨床試験の早期開始を見込んでいます。また,6月にアメリカのYale大学と提携した抗HIV薬Ed4Tの前臨床試験を開始しています。創業2年4ヶ月で「もう」ここまで来たと感じるか,「まだ」ここまでだと感じるか,それぞれ異なった受け止め方があろうかと思います。ただ私個人としては「もう」ここまで来れたことは評価をしつつ,「まだ」まだだと断言したいと思っています。
創薬ゴールへの道は「まだ」果てしなく遠いのです。
- 第31回(6月15日)『大河の如く』
-
「医薬品開発は滔々と流れる大河のようなものである」と,私の製薬企業時代のボスから入社直後に聞かされた言葉です。今では演歌歌手の歌のタイトルのようにしか聞こえませんが。確かに山深い小さな湧き水は創薬のネタ段階。渓谷を迸る渓流がいくつも合わさり,やがて山里を流れる小川となるのは,あたかも化合物スクリーニングを終えていよいよ前臨床に入ろうとする状態。そしていくつもの滝や淀みや大きなうねりを乗り越えて一級河川となり,海へとそそがれる様は,医薬の臨床開発段階そのものの姿であり,医薬品開発のダイナミックさを現して余りある表現だという気がします。
河川が氾濫しないようにするのは人知と技術の粋であり,まさに科学知識と開発戦略で支えられる臨床開発は,自分の経験から振り返っても,大河の流れそのものという実感があります。では,そこに求められる人材とはどのようなものなのでしょうか?欧米式に言えば,例えばMDでありPhDであって,医学知識が豊富で,医学界に人脈があり,社交的で,ビジネスセンスがあり,あらゆる方面への気配りがあり・・・・と切りがありません。まさにスーパーマンかとも思いたくなります。「臨床開発がちゃんと勤まるようなら,どんな業界へ行ってもいい仕事が出来るようになる」とも,よくボスから聞かされました。かくの如く,医薬の開発マンは幅広い守備が出来るマルチプレーヤーであることが要求される訳です。
しかし,最近の流れでは,医薬開発も欧米並みに細分化され,試験実施計画だけ,副作用チェックだけ,医学統計だけ,開発戦略だけ,のようなパートごとの専門職になってしまい,臨床試験ないしは開発計画全体を統括できる人材が日本には非常に乏しくなってきていることも事実のようです。日本の医薬品開発が停滞しているのは,単に医療界や規制当局の問題だけではなく,実は業界にも問題は潜んでいると言わざるを得ません。
当社のようなベンチャー企業のプロジェクトでも,今は細々とした流れでも,いずれは大河の如く,滔々とした流れを作ってゆくことになるはずです。テロメライシンはさしずめまだ山村を流れる渓流で,もうすぐ一級河川の上流に差しかかろうというところでしょうか。この河を守る番人たちは,みな野心を持って集まってきたそれぞれのエキスパートであり,同時にお互いを支えあうことが出来るマルチプレーヤーでもあって欲しいと願っています。そして,いつの日にかこの河が大海に注がれてゆくことを,薬を待っている患者さんと共に,今から夢に見て。
- 第30回(6月5日)『一貫性,そして継続性』
-
今年もアメリカ遺伝子治療学会(第9回)に参加してきました。かつての造船と鉄鋼の街,ボルティモアで開催されました。今ではその面影は薄れ,シーフードの美味しい美しい港町に生まれ変わっていました。
今回も学会は盛況で,昨年同様,総演題数は1100を超え,欧米やアジアから総勢2500名を越す参加者が集まりました。その中で当社の発表は6題あり,ポスター前では様々な研究者とのディスカッションが繰り広げられていました。また,中国や韓国の研究者の台頭が目覚しく,果敢に研究に取り組む姿勢が伺われました。
さて,本家本元のアメリカの状況はどうか?はっきり言える事は,一貫して遺伝子治療やウイルス療法が途絶えることなく,これでもかと言う位に継続的に研究されていて,それらが続々臨床試験段階に入ってきているということです。さらに,これまで遺伝子治療と言えば,アデノウイルス,アデノ関連ウイルス,レトロウイルスが主流で,ウイルス療法には更にヘルペスウイルス,麻疹ウイルス,或いはニューキャッスルウイルスが加わる程度でした。ところが,今回の報告では,コクサッキーウイルス,Seneca Valley Virus,Vaccinia Virus,Vesicular Stomatitis Virus,Parvovirusなど,様々な抗腫瘍効果を持ったウイルスの研究が大学やベンチャー企業で開始され,将来の臨床応用が検討されていました。
Introgen社もADVEXIN(Ad-p53)の上市を見据え,大きなシンポジウムを開き,Merck製薬はHIV感染症のワクチンをアデノウイルスを用いて行ったPhase Iの報告を行い,ベンチャーの老舗Genzyme社も学会の大きなスポンサーとなり,アデノ関連ウイルスベクターを用いた様々な臨床応用を報告していました。このように,製薬企業のこの分野での動きも益々活発になってきています。
当社は現在,テロメライシンのPhase I開始に向けて,FDAからの宿題を着々と片付けています。この学会にも,テロメライシンを評価したFDAのメンバーが多数来場しており,彼らとの非常に有意義なディスカッションも出来ました(日本とは随分違います)。間もなくFDAからの宿題に対する回答が可能になると思います。当社も,この新しい治療法の一角を担っているという自負を持ち,ウイルス療法開発に対して,一貫性と継続性をこれからも維持してゆきたいと考えています。
- 第29回(5月15日)『戦いはまだ続く』
-
昨年秋に母親が重症の脳塞栓で病に臥しました。若い頃からの心房細動体質で,血栓が脳に飛ぶことを注意していたにもかかわらず,ある朝突然意識が混迷し,病院に運ばれました。検査したときは既に中大脳動脈の塞栓が両側にわたるものであることがわかり,明日をも知れぬ病状でしたが,幸い脳浮腫を抑制する薬が効いたのか,一命を取り留める事は出来ました。しかし,それ以来母は一度も物事を認識することがなく,経腸栄養だけで生命をつないで生きています。
医薬品はどこまで効くのか?この命題を,私はこの業界に入って以来ずっと考え続けてきました。医薬品として最大の発見であるインスリンも,糖尿病患者の血糖を下げることは出来るものの,糖尿病そのものを治すことは出来ません。抗生物質は体に感染したバクテリアを殺すことが出来るだけで,感染症から立ち直るのは患者本人です。まして抗がん剤はどれだけがんを克服してきたのでしょうか。いまだに死亡原因のトップががんであることを考えれば,自ずと分かることです。
近年,医学部の学生自体は減少していないにもかかわらず,産婦人科や小児科に入局する医学生が極端に減り,社会問題になっています。更に先日の新聞によれば,全国86医学部の中で,何と23学部で脳神経外科志望がゼロであったということです。高い医療技術が必要で,手術時間も長く医療現場に長時間拘束されるような「きつい」診療科は人気がなくなってきているようです。かつて,医学を志した学生の人気の的であった診療科にもかかわらずです。このままでゆけば,我々は将来重病に罹ったときには,わざわざ海外に行って診療を受けなければならない日が来てしまうのかもしれません。
私がこの医薬業界に携わるようになって既に20年以上が過ぎてゆきました。しかし,母の病気に対して,あまりにも無抵抗な自分が情けなく,医学の発展とは一体何だったのだろうか,今一度考えさせられました。病気の治療法の開発はまさに日進月歩なのでしょう。夥しい医学の発見は後を絶たず学会誌に発表され,それを病気克服のために生かそうと,多くの研究室や企業がたゆまない努力を続けています。しかし,まだ人類は一つの病気も治せていないのが現実です。まだまだやることはいくらでもあるのだ,へこたれるんじゃない,という母の声が,病床から聞こえてくるような気がします。
- 第28回(5月1日)『寒肥を撒く』
-
人間は一つの大きな作業を終えると,安堵感共に一種の虚脱感を覚えるものだと思います。大企業と異なり我々のような規模の小さなベンチャー企業では,一旦大きな波が通り過ぎると,昨日までの深夜残業の繰り返しが嘘のように思えてしまうほど仕事がなくなってしまうことに気付くことがあります。しかし,それはとんでもない勘違いでしょう。実際には先延ばしにしていたような仕事が机上の書類の山の中や,引き出しの片隅に残っているはずなのです。それにもかかわらず,はたと昨日までの延長線が見えなくなってしまうのは,虚脱感の成せる業なのでしょう。
故人の言葉に「寒肥を撒く」という言葉があります。私はこれまで,大仕事を終えてやや気が抜け始めてきた社員に対してよくこの言葉を引用してきました。荒れた冬の畑で木枯らしが吹きすさぶ中,農夫らはせっせと肥しを撒き,畑に栄養分を充満させ,来る春には立派な野菜が育つことを願うのです。荒んだ季節に努力してこそ春の成功が訪れるという意味です。
当社は近い将来の株式公開に向け,パイプラインの進捗に最善の努力を傾けています。日々仕事の大きな達成感があるのですが,その裏側には時として虚脱感が潜んでいることもあります。そうでなくとも気が滅入るようなことの多いベンチャー経営です。アゲインストの風が吹いている時こそ「寒肥を撒く」絶好のチャンスだと思います。それは何も仕事(Creation)のことだけではなく,普段出来なかったようなRecreationに敢えて時間を割くのもいいのではないでしょうか。物事の見方が変わるかもしれません。話は少し変わりますが,自己管理の上手い下手を見分ける一つの方法は,風邪引きの時の対処を見ればよく判るような気がします。根性論が先走るような人は,無理して出社して,遅くまで残業して,結局もっと風邪を拗らせてしまって,結果的に長期休暇を取らざるを得なくなる。要領のいい人は,早い時期に短期間しっかりしっかり休みを取り,早々に仕事に復帰する。この違いは大きいように思います。仕事に行き詰ったら,自分に寒肥を撒くつもりで,むしろ休みを取ってでも気分を入れ替えたほうが,その後の仕事の意気込みにも繋がってゆくように思います。
- 第27回(4月17日)『科学用語の翻訳』
-
「バイオテクノロジーの話を聞いてもよく分からないが,何となく期待できるような気がするんだが,心配だ」と言うような呟きを,時折耳にすることがあります。バイオ業界は産業界の中でもやや特殊で専門性が高い分野です。学会などの学術講演はともかく,バイオベンチャーの講演会を聞いてもその内容を理解するのに苦労することが多いように思えます。私のように,この業界に身をおいている人間ですらそうなのだから,業界以外の投資会社の方やパートナリングを求める異業種の方には辛い内容なのでしょう。人のことは言えませんが。
しかし,私個人としては,科学は本来シンプルなものだと思っています。細切れにされた生命現象の仮説を証明するために,複雑で難解な専門用語を散りばめた表現方法を駆使しているのです。しかし,残念なことに,それを万人に分かり易く説明する努力に欠けているために,難解な内容になっているのです。例えば,何故頭痛がするのか?何故この薬は頭痛に効いたのか?という初歩的な生理学・薬理学の問いを考えてみてもいいでしょう。脳血管が収縮しているのか拡張しているのか,出血しているのか梗塞が起こっているのか,それともどこかの神経が圧迫されているのか,といった非常に分かりやすい言葉での表現が可能だと思います。それを,血管収縮性の生理活性物質の3種類あるα,β,γ受容体の一つに競合的に拮抗する薬剤が,細胞内シグナルのリン酸化反応を阻害することによってNFκBへのシグナルが抑制され・・・などとなってくると,理解しようとする意気がやや失せてくる方も多いでしょう。
オンコリスバイオファーマは,がんのウイルス療法剤テロメライシンを実用化するべく立ち上げられました。そのウイルスは,がん組織特異的な制限増殖型アデノウイルスで・・・・などという説明は,結局あまり人には理解されるものではなくて,実はある特定の世界だけでしか通用しない言葉使いなのかも知れないと思っています。私はもっとストレートに,オンコリスは病気(がん)を治す薬屋さんです,と言いたいのです。バイオだろうがケミカルだろうが,医薬品は人を救ってなんぼのもの。難しい話や最先端科学を駆使しても,治療効果が上がらなければ意味はないのです。科学を出来るだけ分かりやすく翻訳し,様々な分野の方々に理解できるようにし,そして,相互のテクノロジーを結合させて更に開発を推進することが大切なのだと思います。科学の翻訳,それもバイオベンチャー社長の大切な仕事の一つだと思っています。
- 第26回(4月3日)『臨床データに潜む人生』
-
先日,当社のアメリカでの臨床試験開始申請(IND)に関するニュースが新聞やウェブサイトに掲載されました。テロメライシンのINDは起業以来の最初の大きな目標であり,これがFDAから了承されれば,手前味噌ですが,日本企業発の初めてのウイルス製剤による臨床試験となるはずです。
事実,マスコミの力とは大きいもので,ニュース報道の後にいろいろな方々からご連絡を頂きました。なかでも,旧友や恩師からの声援は大変に勇気付けられるものでした。それと同時に,数多くの問い合わせが,がん患者さんやその御家族の方々から寄せられてきました。電話であり,メールであり,いずれも切実なもので,一刻も早くウイルス療法を受けたいのだが,どうすればいいのかというものでした。
テロメライシンの臨床試験は今年5月後半より,アメリカ合衆国テキサス州のダラスにある臨床試験専門病院で開始される予定で,主にテロメライシンの安全性を確認することが目的になっています。始めはやや低い投与量で開始され,次第に投与量を高めてゆくやり方で,最大24名の固形がん患者さんを対象とします。
テロメライシンはまだ臨床での安全性と有効性が確認できてはいません。これからそれらの検証を進めてゆきます。もちろんアメリカだけではなく,日本のがん患者さんにも新しいウイルス療法が受けられるよう最大限の努力を傾けてゆきたいと考えています。しかしながら,今すぐ当社のアメリカでの臨床試験にご参加下さいとか,斡旋しますとは申し上げられない現状があることをご理解頂くしかありません。
我々が日々目にする臨床論文には,様々ながん治療の有効性や安全性に関する情報が述べられています。第1相ではせいぜい20例から30例,第2層では50例から80例,第3層にもなれば500例以上の症例が組み込まれることになります。その結果として,縮小率が35%とか,生存期間が5ヶ月延びたと判定されています。これはあくまで,科学的な冷たい数字の羅列であり,物事の客観的評価には必要なことだと考えます。しかし,このような臨床試験に組み入れられた症例1例毎には,それぞれの人生の身につまされる物語があることも事実なのです。100例の臨床試験には100のドラマがあるのだと考えないわけにはゆきません。そこに思いを寄せる気持ちに立脚しない限り,抗がん剤の開発はありえないのだという認識も新たに,これからの臨床試験に取り組んでゆきたいと考えています。
- 第25回(3月15日)『新薬開発の道遠し』
-
先月アメリカ食品医薬品局(FDA)はEGF受容体抗体Erbitux(OSI / Bristol-Myers Squibb社/Merck KGA)を大腸がんに続く適応症として,頭頚部がんに対する適応承認を支持すると発表しました。久しく頭頚部がんの領域に新薬がなかったこともあり,医学会や医薬品業界などに少なからず影響を与えることになりそうです。
頭頚部がんは文字通り舌・顎・咽頭・喉頭・頚部に発現する腫瘍の総称で,これまで放射線療法やいくつかの古典的な化学療法剤を併用して治療が行われてきましたが,これらの治療法は副作用も強く,また手術も著しくQOLを低下させ,その予後は必ずしも良くないと言われています。大相撲の先代二子山親方がやはり頭頚部がんで鬼籍に入られたことは記憶にも新しく残っています。
頭頚部がんと言えば,当社のTelomelysinも同様の領域を適応症の一つと考えていますし,また海外のがん遺伝子治療やウイルス治療を手がけているバイオ企業も,同じ適応症ですでに開発の最終段階に入っています。昨今流行の抗体医薬がこの領域に参入してしまっては,もうがん遺伝子治療やウイルス療法は参入の余地が縮小されてしまうのではないか,と思われる向きもあるかと思いますが,私はそうは思っていません。基本的にがんと言うのはしぶとい病気です。治療薬の種類は多い方が治療のバリーエーションが広がるというメリットがあり,いかにこれらを上手く組み合わせて治療をしてゆくかが今後の課題であることは間違いないと考えます。
さて,この抗体治療,どれだけの効果が示されたかについては,英国医学会誌(N Engl J Med 2006;354;567-78)に,局所進行性の頭頚部がん患者を対象にした第Ⅲ相臨床試験の結果として詳しく述べられています。即ち, Erbituxと放射線療法を組み合わせた群では,その生存期間が,放射線単独療法群の29.3ヶ月から49.0ヶ月に統計学的に有意に(p=0.03)延長したという結果です。しかしながら,そのEditorであるMarshall Posner博士とLori Wirth博士(共にHarvard Medical School)はこの結果に対して「現在の頭頚部がんに対する基本治療はシスプラチンを主体とする化学療法であり,その療法との上乗せ比較試験が実施され,それに対する上乗せ効果が実証されない限り,Erbituxを頭頚部がんの第一選択薬とするべきではない」と,厳しい意見を述べています。
このように,新薬は承認された後でも,まだまだ医薬品として完成させなければならない課題が数多く残されているのです。そのような状況で,抗体医薬に続く新しい手段が望まれていることは明らかなことです。我々も,このさき山のように積まれた課題を一つずつ片付けて行かねばなりません。間もなく当社はTelomelysinをFDAに治験申請(IND)しますが,新薬開発の道はまだ遠い。
- 第24回(3月1日)『原則規制』
-
先日ニューヨークに出張する機会がありました。大雪が降る前で,連日好天気に恵まれました。私はその朝,喧騒のミッドタウンを歩きグランドセントラルからのコネチカット方面への列車へと急いでいました。ブロックごとの信号で,私は「止まれ」という手形の赤信号で大人しく立ち止まった。しかし,ニューヨークの人々はそんなの無視,信号がどうであろうと車の間隙を衝いてどんどん通りを渡ってゆく。立ち止まったまま車のやってこない通りを眺めてリズムに乗り切れていないもう一人の東洋人風の男とは目を合わさないようにした。
何故信号で止まらなければならないのか?と問われれば,「赤だから」と日本人は答え,「ひとつの目安だから」と欧米人は答える。ここに「原則規制,一部自由」の日本と「原則自由,一部規制」の欧米との間に根本的な考え方の違いがあると養老孟司氏は述べています(「こまった人」 中央公論新社刊)。これは「個人主義」の成熟度に関わっていると私は感じています。自己に帰するべき責任の範囲をどのように認識するかは日本と欧米では微妙に異なっていると感じています。
振り返ってみて医薬品の世界。規制当局の考え方も日本と欧米ではどうも大きな違いが存在しているように思えてなりません。例えばアメリカはどうか。当社が経験してきたFDA(アメリカ食品医薬品局)との会議で感じたことは,まず「規制」ありきという姿勢が感じられなかったことです。つまり,我々の研究成果がある一定のレベルを超えていれば,あとはどのようにガイドラインを解釈しても結構であり,その会社の責任のもとにしっかりと前に進んでゆき,必要であればFDAはいつでも相談に乗ります,という姿勢なのです。同様に企業側も,ガイドラインをどのように自分達独自の形にアレンジするかをまず考えるでしょう。つまりガイドラインは規制ではないと認識しています。
では日本の規制当局である厚生労働省はどうでしょうか?私の多少の経験からみて,どうやらまず「規制」ありきであり,個別の対応に時間がかかり,ハードルが必要以上に高くなることもあります。特にバイオ医薬品の場合には治験開始が遅れることもしばしばであるようです。日本でも様々な医薬品開発に関するガイドラインが公表されています。しかし日本人はこれを守るべき「規制」と考えがちであり,それさえ守っていれば大丈夫,という一種の思考停止状態を企業側も作ってしまっている面もあります。
赤信号で無意識に止まっていれば安全度は高まり,そのような思考停止状態は私にとっても非常に楽なことです。しかし,リスクを取るべきベンチャー企業の経営者としては,もしかして失格なのかも知れません。
- 第23回(2月15日)『企業倫理について』
-
いま企業倫理が世間では問われています。一世を風靡したIT企業や建設会社が槍玉に挙げられ,急速に没落してゆく様を見ていると,栄華が過ぎ去ったあとの荒野を見る思いがしています。いずれの例を見ても,責任のなすりつけ合いは共通して起こっていて,何処に反省があり,どのように改善してゆこうとしているのかさえも読み取れない状況です。
さて,創薬企業に置き換えた場合の企業倫理とは一体どのようなものなのでしょうか?一企業として,管理体制整備やコンプライアンスを遵守することは至極当然なことでしょう。ただ,製品である医薬品は,人の病気を救うこともあるが,時には副作用で人を傷つける場合もある,と言う事です。医薬品メーカーだから他の企業に比べて倫理観は高いはずだ,抗がん剤は人の苦しみを救うから役に立つはずだ,といったキーワードだけで企業倫理を片付けてはいけないと考えています。医薬品のよい面のみがクローズアップされることは非常に危険なことだと,経験上身にしみて感じています。
当社はアデノウイルスを基礎にしたがん治療法を開発しています。これまでの欧米での数多くの臨床成績から,アデノウイルス自体の安全性には大きな問題はない,と一応知識の上では考えています。また,化学療法や放射線療法に比べれば,問題にならないほどの副作用だ,とも感覚的には考えています。しかし,医薬品は必ず副作用を発現するものです。徹底的に副作用のない医薬品を求めると,新薬は存在しなくなるでしょう。これも経験上真実だと思います。それでも創薬企業が医薬品を開発しようとするのは何故か。やはり臨床効果と副作用のバランスを考えるしかないのでしょう。
かつて,抗ウイルス剤を開発していたメーカーが副作用(死亡例)を隠し,社会的に大きな問題となったこともありました。薬害エイズ問題はまだ記憶に新しいと思います。近年では,アメリカの最大手製薬企業が発売していた抗炎症剤が,長期服用により合併症発現率を上昇させると分かっていながら,大きなセールスを確保するために販売を続けて裁判沙汰になっていることもご存知かと思います。
つまり,創薬企業だから倫理観が高いだろう,という短絡は許されないと思います。それは思い上がりでしょう。企業倫理とは,どんな種類の企業においてでも,自らが苦労して,時間をかけながら作り上げてゆくものなのだと,私は信じています。
- 第22回(2月1日)『第24回Healthcare Conferenceに参加して』
-
1月9日から12日にサンフランシスコで盛大に行われたJP Morgan主催の第24回Healthcare Conferenceに参加してきました。バイオ企業,製薬企業,証券アナリスト,報道関係など想像を超える数の聴衆が押しかけ,今回も300を越すヘルスケア関連企業からの決算報告や2006年度の方針が,経営者自身のプレゼンテーションで報告されました。これまで長い間業界誌やニュースなどで名前だけ知っていたようなバイオ企業の内容なども窺い知ることができ,アメリカでのバイオ産業の底の深さを身にしみて感じてきました。
アメリカのバイオ産業は既に20年以上の歴史を持っており,Amgen,Genentech,Genzymeといった老舗バイオの講演には,広大なホールの外にまで立ち見が出るほどの関心が寄せられ,ロビーはまるでバイオ同好会の集まりのように,企業の壁を超えたディスカッションに花が咲いていました。
私がかつて評価検討をし,このバイオベンチャーのこのようなネタではとても将来立ち行かないだろう,と思っていたような会社でも,どっこいまだ健在で,その後も増資を重ね,ビッグファーマと提携を結び,更にパイプラインを増やして臨床試験に臨んでいる,なんて言う会社も数多く見受けられました。彼の国では,ベンチャーの経営者もしたたかながら,それを支える投資環境も違ったものがあるようです。
日本ではこのような催しを行うのはまだ時期尚早のような気がします。何故ならば,カンファレンスの報告内容の主流を占めていたのが,第2相や第3相臨床試験の結果であり,更にその後の営業方針であり,磐石な経営内容だったからです。そういった創薬ベンチャーが100を超えるほども集まり,またそれを評価する企業やアナリストが何千人も集まるような環境は,残念ながら日本では程遠いのかも知れません。
明らかなのは,当社はまだ弱小バイオベンチャーであり,創薬に向けてほんの一歩を踏み出したばかりの発展途上企業なのだということです。カンファレンスに居並ぶバイオ企業と肩を並べるにはまだまだ大きな山も谷も越えてゆかなければなりません。とは言え,今回は大変によい刺激を受けることが出来たように思います。将来のオンコリスバイオファーマのあるべき姿を頭の中で組み立てながら,サンフランシスコからの岐路につきました。
- 第21回(1月16日)『2006ダッシュ』
-
2006年も明け,弊社もいよいよ創業3年目に入ることになります。主力開発品であるテロメライシンは,昨年アメリカFDAとのPre-IND会議を終え,今年はいよいよ臨床試験が開始される運びとなってきました。また,テロメスキャンの診断薬としての研究も着実に進歩を遂げてきました。今年前半には第三者割り当てによる増資を計画しており,がんのウイルス治療を始め,今年からは更に感染症治療薬のパイプラインも充実させるよう努力してゆきたいと考えています。オンコリスバイオファーマ株式会社は創業期から成長期へ向かう第二の段階に差し掛かってきていると言えるでしょう。将来の株式公開に向け,今年はスタートダッシュをかけるべき非常に重要な1年目になることは言うまでもありません。
日本の医薬品業界は,今年も薬価切り下げの年中行事に始まり,合併して巨大化した製薬企業は,益々大型新薬の開発に資源を注がなければならなくなり,一方で新薬開発は益々海外に流出し,日本の臨床試験の空洞化は,医薬品総合機構の意気込みとは裏腹に,益々進んでゆくことになるでしょう。また,世界に目を向ければ,メガファーマと呼ばれる製薬企業も,主力商品の特許切れが目白押しとなってきており,その補填のための新薬開発に躍起とならざるを得ない状況です。そのために,市場性が必ずしも大きくはない画期的新薬(アンメットメディカルニーズ)の芽がなかなか育っていないのが現状です。
このような状況の中で,着実に成長を遂げている創薬ベンチャーの存在意義は世界的に益々高まってゆき,これからも製薬企業との提携が進んでゆくものと確信しています。
本年も宜しくご指導下さいますよう,宜しくお願い申し上げます。